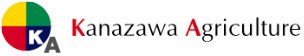12月31日。
久しぶりの休日に、今年一年を振り返ってみた。
今年は、有機麦類・有機大豆の収量が極端に悪かった。
栽培技術の問題もあるが、昨年麦播種期・本年の大豆播種期の天候不順が減収の原因になったと思う。
10月から12月にかけて行う来年産の麦播種は、おおむね順調だったし、大豆作での新しい雑草対策に道筋が立ったので、来年の実りに期待したい。
新しい農業生産法人も立ち上げ、農場のスタッフも増え充実してきた。
来年は、結果を意識した良い年にしたいと思う。
さて、自民党から民主党に政権交代して、来年度から新しい農業政策「戸別所得補償モデル対策」がスタートする。
新政権発足後から「新しい制度についてどう思いますか」こんな質問を受けることが多かった。
年末になり、予算も確定し、その仕組みの詳細も発表された。
自分なりに少し考えてみた。
私のミッションである「自給率の向上」「耕作放棄地の減少」この二つに絞って考えてみると、賛成である。
まず、戦後の農政は、上記二点については結果を出してこなかった。食料自給率40%、耕作放棄地38万ヘクタールの現状を打開するには、思い切った農政の方向転換が必要であり、その意味では大きな改革の一歩として期待している。
■「戸別所得補償モデル対策」について評価する点
日本の米作を「食料自給率向上の主役」と見直した点である。適地適作の考えが盛り込まれており、生産調整とセットで、不適地(水田)で無理やり大豆・麦の振興を行うよりも、理にかなっている。
何度も言うように、日本の水稲は世界に誇れる農業であり、持続性の有るシステムなのだ。
もう一点は、兼業農家等の小規模農家に対しても支援することで、都市部や中山間地等、条件不利地での水田荒廃の歯止めに期待ができる点である。農家の六割が65歳以上であり、担い手の掘り起こしと、農地の保全は、待ったなしである。
制度がシンプルな点も評価できる。
■「戸別所得補償モデル対策」に関連して思うこと
財源の問題もあるだろうが、米の価格維持政策からの決別が必要である。
個人的に戸別補償制度と生産調整の廃止は、セットで行われるべきだと思う。
兼業農家も含めた農家にこれだけの国庫を投入するからには、同時に農業の産業としての成長戦略を示すか、米価下落により家計負担が減る、米の市場開放により輸出関連産業の成長を促すなどが必要である。
専業農家としては、農業の産業としての成長戦略を是非一緒に考えて欲しい。
■新しい農業政策について
お米を中心とした、土地利用型大規模穀物農家の立場からすれば、自民党政権終期に、品目横断的経営安定政策が始まり、担い手へ施策が集中することに対する期待感が有った事は事実である。
今まで、構造改善事業などの農業土木や、関係団体に付いていた予算が、直接農業の現場である担い手に支払われるようになったことも評価できた。
さて、常々思うのだが兼業農家や集落営農等の個人資産の継承、治水や環境保全に軸足を置いた農家と、産業としての農業経営体に対する農業関連予算を別に考えることはできないだろうか。
つまり、成長産業として育てるべき農業と、国土保全・農村振興として守るべき農業のプレーヤーに対して使命や役割を明確に線引きし、個々の経営に着目した政策を打てないだろうか。
例えば、「戸別所得補償モデル対策」は、兼業農家に絞り、国土保全に協力していただく。専業農家は「戸別所得補償」ではなく、経営改善計画等将来の目標設定や、その達成度・プロセスや成果を評価し、補助金が支給されるような仕組みにはならないだろうか。
兼業農家と専業農家の役割や使命を明確にし、政策目標を数値化した上で、その達成度に応じて評価する仕組みである。
シンプルはいいが「十把ひとからげ」では、農政は行き詰まる。
色々な意味で、多様性を大切に考えなければならないと感じる。