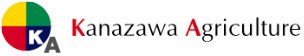さて、私の職場である河北潟干拓地の現在。
適地適作、地域性を考えずに進めた畑地化の失敗。
酪農団地の苦悩。
水稲の規模拡大を夢見、増反を希望した多くの農家が、水田→畑地への地目変更に失望し去っていった。
そして、畑作に挑戦した多くの先輩達も野菜の産地化を達成できず去ってゆく。
私が就農した11年前は、耕作放棄地が10%近くもあり、葦(ヨシ)だらけの荒地が目立った。
元来沼の底であった河北潟干拓地の土壌は、重粘土(陶器が焼けそう)で腐食も少なく、物理性が極端に悪いのだ。
雨が降れば湿害(水はけが悪い)
干ばつが続けば、石のように硬い泥の塊が作業効率を悪くする。
雑草の種類、量も半端ではない。
お米ならば3年間くらい無肥料で栽培できる肥沃な湿地帯。
何故、ここを畑地に誘導したのだろうか。
実際、レンコン団地の営農は順調である。
「米あまりによる国の新規開田抑制通達」この通達が全てである
この通達が河北潟干拓地の現在を決めたと言ってもいいだろう。
現在は、麦・大豆二毛作による土地利用型大規模経営農家が数人で、その多くの農地を管理している。
最近では、過去の実績による補助金を受けながら、加工米の生産に取り組む農家も増えてきた。
反収150キロの大豆、300キロの大麦を栽培するよりは、たとえ安くとも(6千円/60kg)の加工用米を生産したほうが所得が上がる。お米の収量は苦労なく反辺り500kgを超えるのだ。
私はと言えば、約10年間で90haの耕作放棄地を耕し規模拡大してきた。
父親が確立した、麦・大豆二毛作による土地利用型大規模畑作を有機栽培に転換して、悪戦苦闘している。
さて、平成22年に河北潟干拓地は、25年前から払い続けてきた借金(農地の造成のために国から借りていた借金)の償還が終了する。
農政の舵取りしだいでは、多くの農家が畑作を断念し、水稲を生産する可能性もある。
もしかしたら、最後まで麦・大豆の生産を続けるのは、私だけかもしれない。
応援してくださる消費者・流通・実儒者(加工メーカー)への供給責任が有るのだ。
有機栽培そして地産地消の麦・大豆。
険しい道である。