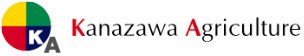2011年3月15日 オーガニックシンポジウムが震災で延期になり、明後日6月10日に開催されます。10分間のリレートークに出演することになりました。皆様とお会いできる事を楽しみにしております。
とことんオーガニックシンポジウムに寄せて。
オーガニックは世界の言葉・地域の営み。
日本の有機農業は、提携や地産地消により、良識ある多くの生活者に支えられ発展してきたと思います。実際に私が脱サラして最初に挑戦したのが、お米と少量多品目の有機野菜を栽培し、地域の消費者や流通と提携する地域の営みでした。しかし、就農して知ることになったのは、農業を取り巻く様々な問題・課題でした。地域の耕作放棄地問題や高齢化等、危機とさえ言える日本の農産業の現実があります。その時、経営理念として掲げたのが「千年産業を目指して」。今風に言えば「サステナビリティ “sustainability”」。これが、私の有機農業の出発点です。近年生活者のニーズ・価値観は多様化し、オーガニック商品に対しても様々な角度からのアプローチがあると感じます。有機農業を目指す若者や有機転換希望者も増え、様々な理念や事情から有機農業への参入に挑戦なさっています。私も挑戦者の一人でしたし、保守的な農業界からは、はじかれる「変わり者」「異端児」であったかもしれません。時は静かに流れ、地球温暖化等の環境問題や、安全・安心な食品の再考の機運により、我々の営みに対する理解者が増えてきました。オーガニックは多様な生活・営み・農業の選択肢のひとつであり、オーガニックは世界の農業・食品・社会システムの代替“alternative”になりうる、とすら感じます。,,さて、私が有機農業を志した頃は、国内に有機認証制度が在りませんでした。つまり、「日本の有機農業の生産行程基準」が無かったのです。「有機とは」なにか?先進的なヨーロッパの有機農業について調べるうちに、第三者による認証が大切なことを知ります。日本では地元の石川県が独自の基準で。JONA(日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会)がIFOMの基準で第三者認証を行っていました。ご縁があり、JONAに相談したことから、私の有機農業がスタートしたと思っています。私は近年、有機農産物の輸出に挑戦しています。前述の提携や地産地消とはかけ離れていると言う方もいらっしゃるかもしれません。その是非は別として、海外の有機農家や流通関係者、消費者と交流すると、「オーガニック」に対する共通の認識が多いことに気づきます。簡単に言うと「オーガニックは世界の言葉」であり「世界の基準」が生まれつつあるということです。”I am an organic farmer in Japan.” 私は英語を話せないのですが、この一言で多くの国の人々に、私の農産物の“Philosophy”を想像してもらえます。共通の価値を認め合うことができるのです。また、疲弊する地方の水田地帯では、減反政策や・米価の下落・米あまりといった、構造的な問題が顕在しています。昨年の後半急に、TPP「環太平洋戦略的経済連携協定(Trans Pacific Partnership)」参加の是非なる議論が始まりました。国の戦略として、FTA・EPA交渉の推進が叫ばれてきたのは認識していましたが、この議論は急すぎるし、突拍子もないというのが私の感想です。日本がTPPに参加すれば、農林水産業への経済的な打撃は大きく、激変に対する策が講じられなければ、日本の農業は壊滅するかもしれません。土地利用型の有機穀物農家として、経営とその持続を考えたときに、私の有機農業は地域の営みであると同時に、世界の動向を理解し、世界に貢献する農業でなければならないと考えるようになりました。輸出に挑戦しはじめて、世界には日本の有機農産物を評価する人々が存在し、日本の有機農産物は世界に広がる可能性があると感じます。美しい水と風土に恵まれた日本の農業は可能性の有る産業なのです。「オーガニックは世界の言葉」新しいオーガニックの可能性が広がっているのです。