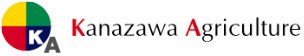一連の事件は、お米をまじめに生産する農家として、そして消費者として残念でならない。
心無い業者や、担当行政の指導管理体制への批判はマスコミにまかせ、今回の汚染米事件から思う米粉流通や米粉の需要拡大の可能性について書いてみる。
さて、今回の事件、流通ルートの全容解明・・・・・・など等
チャートや図で新聞に大きく報道されている。
「お米って、こんなにいろんなところで利用されているのか」
こんな感想を持たれた方は多いのではないだろうか。
日本の食文化は、お米なしには語れない。
焼酎から味噌、おせんべい・・・・・。
粉に形を変え様々な食品に混ぜられているのである。
与党や農林水産省は、米粉や飼料米を水田営農対策、耕作放棄地対策、自給率アップの切り札として、米粉の振興を進めるようだが、冷静に考えてほしい。
今回の「事故米の流通」を検証すれば、価格が安ければどんなものにでも使えるし、実儒者・消費者が口にできることが理解できる。
もちろん、安全が前提であるが。
なにが言いたいかというと。
米粉の生産を振興しなくても、価格さえ下がれば、米の需要は増えるということである。
米の価格政策から決別して、マーケットから評価される「日本の米業界」を育てるべきだと強く思う。
何度でも言う、農林水産省は減反政策から舵を大きく切り、米の価格政策から米の生産振興・利用振興・需要振興へ向かうべきである。
WTOやEPA・FTAがもたついている数年を猶予期間と考え、生産調整を廃止すべきである。
もちろん、米価下落による農民の痛みもあるだろうが、この痛みを乗り越えなければ、日本の米作農家の未来はない。
みかん農家も野菜農家も畜産農家も皆、乗り越えてきた道である。
米価下落を何故恐れる。
古里の田を耕し、国民に安全安心で美味しく、適正価格のお米を安定的に供給する。
この事が農民の使命ではないのだろうか?
道理が有れば、結果はついてくる。
七色の補助金で問題を先送りしても、誰も幸せにはなれない。
耕作放棄地・食糧自給率
この二つを解決するシンプルな方策は、生産調整の廃止である。
慣行米より安い有機小麦を生産する農家が、外麦との相対的な価格差に挑み、苦労してきた。
今現在、こんなに高い日本の米を粉にしたところで、安価な小麦粉と競争できるはずがない。
マーケットはそんなに甘くはないのだ。
もちろん補助金で誘導することに一定の効果はあるだろうが、お米の価格が下がるほうがシンプルである。
最後に一言、もしもお米農家で、農産加工の為に高価な米粉機を購入することを検討している方がいらっしゃるなら「採算性」をよく考えて導入してほしい。
機械に対する補助や作付けに対する補助が有っても、10年先、20年先を考えて欲しい。
一キロ当たり200円前後の玄米を加工して、一体いくらの農産加工品を作ろうと言うのだろうか?
今回の汚染米事件でわかるように、米粉が流通する世界は、クズ米、古々米等の世界。
無責任な米粉振興に国庫を投入することには賛成できない。
汚染米事件報道から思うことである。